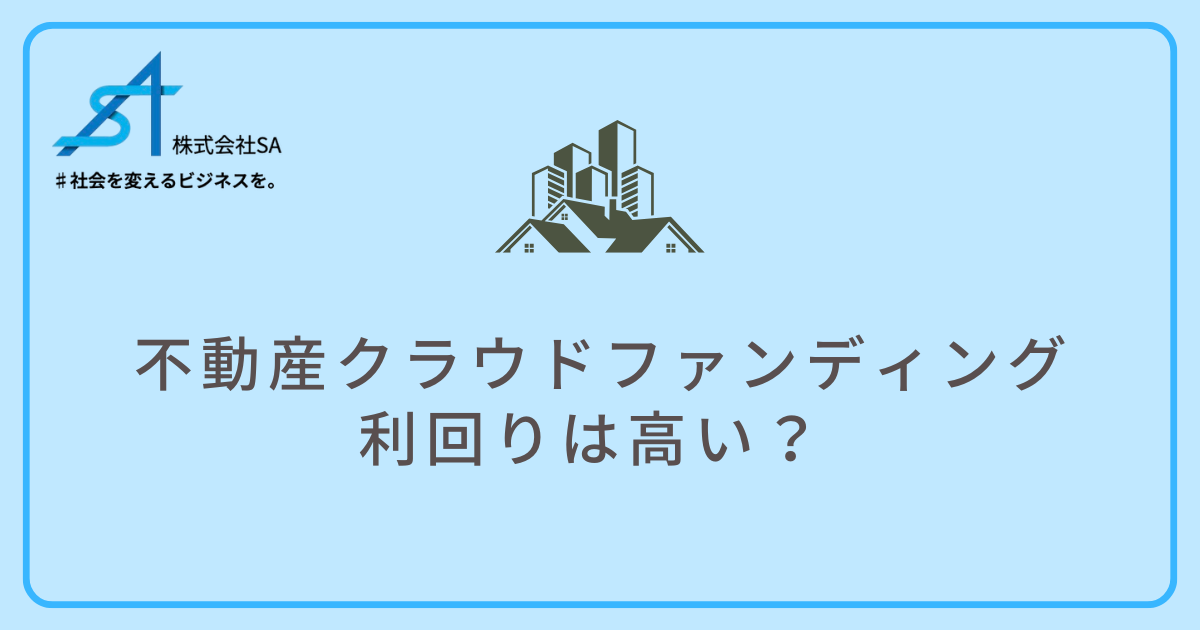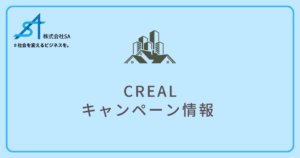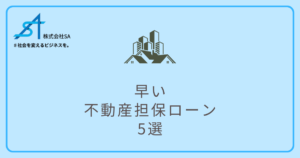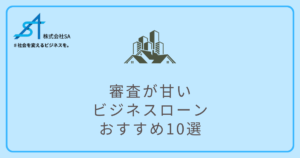「不動産クラウドファンディングの利回りって実際どれくらいなの?」
「高利回りの案件に投資したいけど、リスクが心配…」
そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
不動産クラウドファンディングは、少額から始められる投資手法として注目を集めていますが、利回りやリスクについて正しく理解することが重要です。
この記事では、不動産クラウドファンディングの平均利回りや、他の投資商品との比較、利回りを左右する要因、そしておすすめのサービスまで、詳しく解説していきます。
投資初心者の方でも安心して読める内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
上場企業運営の不動産クラウドファンディング「CREAL(クリアル)」が、Amazonギフトカードのプレゼントキャンペーンを実施中です!

投資家登録だけでも2,000円分のアマギフ、初回投資額に応じて最大48,000円分のアマギフがもらえます。
合計で最大5万円分のギフト券をもらえるお得な内容です。
不動産クラファンを始めたい!という方は、この機会にCREALへの登録を検討してみてはいかがでしょうか。
不動産クラウドファンディングの平均利回りは3~8%
不動産クラウドファンディングの平均利回りは、一般的に3~8%程度とされています。
これは、他の投資商品と比較しても魅力的な水準です。
ただし、利回りはファンドの内容や運用期間、物件の種類などによって異なるため、投資前にしっかりと確認することが大切です。
ここでは、
- 想定利回りとは?計算式と「表示利回り」との違い
- 分配金が生まれる2つの収益(インカム/キャピタル)
- 元本割れリスクと劣後出資による保全スキーム
という3つの観点で比較や解説をしていきます。
想定利回りとは?計算式と「表示利回り」との違い
想定利回りとは、投資家に対してあらかじめ提示される「予定の年間収益率」のことです。
これは投資開始時点で運営会社が計算した「収益÷投資金額×100」の数値であり、必ずしも最終的な実績と一致するとは限りません。
一方、「表示利回り」は、WEBサイトやパンフレットに掲載されている収益率で、多くの場合、想定利回りと同じ数値が使われます。
しかし、実際には税金やキャンペーンなどで手取り額が変動するため、表示されている利回りだけを鵜呑みにするのは危険です。
分配金が生まれる2つの収益(インカム/キャピタル)
不動産クラウドファンディングで得られる収益は大きく2種類あります。
- インカムゲイン:物件の家賃収入から得られる定期的な収益
- キャピタルゲイン:物件の売却益によって得られる一時的な収益
必ず片方だけが適用されるわけではなく、インカムゲインとキャピタルゲインを組み合わせたファンドも多く存在します。
これにより、安定性と収益性のバランスを取った運用が可能です。
元本割れリスクと劣後出資による保全スキーム
不動産クラウドファンディングには、元本割れのリスクがあることを忘れてはいけません。
予期しない空室や物件価値の下落などにより、予定通りの収益が得られないケースもあります。
そこで重要なのが「劣後出資」です。
これは、運営会社自身が先に損失を負担する仕組みで、投資家が出資する「優先出資」のリスクを一定程度カバーする役割を果たします。
一般的には、劣後出資割合が20%以上ある案件は安全性が高いとされており、ファンド選びの重要な指標となります。
インカムゲインがメインの案件では高めに、キャピタルゲインがメインの案件は低めに設定されることが多いです。
他の投資商品の利回りと徹底比較
不動産クラウドファンディングの利回りは魅力的ですが、他の金融商品と比べてどうなのでしょうか。
ここでは、代表的な投資商品と利回り・リスクの違いについて詳しく見ていきます。
預貯金・国債・社債との安全性&利回り差
預貯金や国債は、元本保証があるのが大きなメリットです。
しかし、利回りは0.001~0.05%程度と非常に低く、インフレ時には実質的な資産価値が目減りする恐れがあります。
一方、社債は企業の信用力によって異なりますが、利回りは0.3~1.5%程度が一般的です。
これらと比較すると、不動産クラウドファンディングの3~8%という利回りは、かなり高水準であることが分かります。
J-REIT・株式配当と比べたリスク/リターン
J-REIT(不動産投資信託)は、不動産クラウドファンディングと似た運用形態ですが、株式市場で売買されるため価格変動リスクが高くなります。
配当利回りは3~5%が相場であり、安定した収益は期待できますが、景気の影響を受けやすいのがデメリットです。
個別株の配当利回りも2~4%程度と、不動産クラウドファンディングと同等かやや低めです。
現物不動産投資とクラファン利回りのギャップ
現物不動産投資では、収益性の高い物件を選べば10%を超える利回りも狙えますが、初期費用が高額で、管理・修繕の手間もかかります。
一方、不動産クラウドファンディングは、手間をかけずに分散投資ができ、運営会社が管理を代行してくれるというメリットがあります。
そのため、同じ不動産を扱う投資でもクラウドファンディングは「手軽さ」と「安定性」を重視する人向きです。
利回りを左右する4大要素
不動産クラウドファンディングにおいて、利回りを決定づける要素はいくつかあります。
ここで紹介する、
- 物件種別・立地が利回りに与える影響
- 運用期間と出口戦略──短期高利回りvs長期安定型
- 劣後出資割合・LTV・ローン比率のチェックポイント
- 運営会社の手数料・キャンペーンで実質利回りが変わる
の4つは、特に重要なポイントとして押さえておくべきです。
物件種別・立地が利回りに与える影響
物件の種類(マンション、オフィス、商業施設など)や立地条件は、利回りに大きな影響を及ぼします。
一般的に、都市部の不動産は取得価格が高くなりやすく、その分利回りは低くなる傾向があります。
一方、地方の不動産は取得価格が比較的安価であるため、表面的な利回りは高く見えることが多いです。
ただし、地方物件は空室リスクや流動性の低さといった懸念があるため、利回りだけで判断するのではなく、収益性と安定性のバランスを見極めることが重要です。
運用期間と出口戦略──短期高利回りvs長期安定型
運用期間が短いファンドは、キャピタルゲイン狙いで高利回りが期待できますが、リスクも比例して高くなります。
逆に、長期運用型はインカムゲイン中心で、利回りはやや低めでも安定した収益が得られる点が特徴です。
投資目的に応じて、期間の長短を見極めることが重要です。
劣後出資割合・ローン比率のチェックポイント
利回りの安全性を見極めるために、以下の数値に注目しましょう。
- 劣後出資割合:20%以上であれば損失耐性が高い。
- ローン比率:借入金が多いほどリスクも増す。
これらを確認することで、案件のリスクと利回りのバランスが把握できます。
手数料・キャンペーンで実質利回りが変わる
運営会社が設定する手数料(管理費、運用報酬など)は、想定利回りから引かれることがほとんどないですが、出金手数料や振込手数料は追加でかかってしまいます。
サービスによっては、特定の銀行を使用することにより、手数料を抑えられるケースもあるため、確認しておきましょう。
また、期間限定のキャッシュバックやボーナス利回りキャンペーンなども加味すると、手取り収益が大きく上がることもあるので、情報収集を怠らないようにしましょう。
不動産クラウドファンディングおすすめサービス【高利回りから低利回りまで】
数あるサービスの中でも、実績・利回り・安全性のバランスに優れた不動産クラウドファンディングサービスを2つ紹介します。
COZUCHI(平均実績利回り17%超え)

COZUCHIは、都心部の不動産を中心に運用するキャピタル型ファンドが特徴です。
年利4~13%と高利回りを狙える案件が多く、途中解約可能なファンドもあるため、流動性の面でも安心できます。
また、利回りの上振れが起きることもあり、これまでの平均実績利回りは17%を超えます。
高利回りファンドを多く組成していますが、これまでに元本割れは0件です。
ただし、取り扱う不動産は利権関係が複雑な案件も多く、インカムゲインがメインのサービスに比べるとリスクは高めです。
CREAL(平均利回り4.3%)

CREALは、賃料保証付きの物件に投資できる点が大きな特徴です。
マンションだけでなく、学校や介護施設などの大型物件に分散投資できるため、リスクの軽減にもなるでしょう。
多くのファンドがインカムゲインがメインで、4.3%程度の安定した利回りを実現しています。
最近では利回りも上昇傾向にあり、4.3%の利回りでは物足りない方でも投資検討できるのではないでしょうか。
利回りだけに惑わされないサービス選び3つの視点
利回りが高いからといって、必ずしも良い案件とは限りません。
そこで投資判断においては、次の3つの視点を持つことが重要です。
- 高利回り=高リスク?案件情報を精査
- 劣後出資比率20%以上を目安に安全性を判断
- 運用期間を確認
高利回り=高リスク?案件情報と担保・保証を精査
利回りが高すぎる案件には、相応のリスクが潜んでいる可能性があります。
しかし、高利回り=高リスクというわけではありません。
そのため、想定される出口戦略などを細かくチェックし、リスクを適切に評価するようにしましょう。
劣後出資比率20%以上を目安に安全性を判断
前述の通り、劣後出資割合が高いほど、投資家の元本が守られる可能性が高くなります。
そのため、例えば劣後出資比率が20%の場合、物件価格が20%下落しても、投資家の出資(優先出資)には影響が出ない構造になります。
このように損失の“クッション”となる割合が一定以上あることで、投資家にとってのリスクを抑える効果があるため、20%以上を一つの目安とするケースが多いのです。
運用期間を確認
不動産クラウドファンディングは比較的短期的な投資ですが、途中解約ができないケースがほとんどです。
そのため、近い将来使う予定のあるお金を投資に使ってしまうと、いざというときにお金が足りなくなってしまうこともあるでしょう。
運用期間が伸びることもありますので、資金計画には余裕をもち、運用期間は必ず確認しましょう。
利回りを最大化する3つのコツ
利回りは単に「高い案件を選ぶ」だけでは最大化できません。
実質的な手取り収益を増やすために、以下の3つの工夫が効果的です。
- 複数サービスの利用で抽選落選リスクを低減
- キャンペーン/キャッシュバックで実質利回り+α
- 源泉徴収後の手取り利回りを意識し確定申告で控除を活用
複数サービス併用で抽選落選リスクを低減
人気の高いクラウドファンディングサービスでは、抽選制が一般的です。
そのため、1社のみに依存せず、複数のサービスを併用することで、抽選落選のリスクを軽減し、常に運用資金を稼働させることが可能になります。
また、投資は分散が原則です。
- インカムゲインがメインのサービス・キャピタルゲインがメインのサービス
- 都心の不動産・地方の不動産
など、分散できるものは分散しておくことをお勧めします。
キャンペーン/キャッシュバックで実質利回り+α
各社が不定期で実施するキャンペーンやキャッシュバックは、表面利回りに上乗せ効果があります。
たとえば、
「新規登録で1,000円分のAmazonギフト券」
「投資額の1%を還元」
といった特典が、実質利回りを大きく押し上げる要因になります。
これらは公式サイトやメールマガジンなどで告知されることが多いため、事前に登録しておくのがおすすめです。
源泉徴収後の手取り利回りを意識し確定申告で控除を活用
利回りを考える際には、「税引き後の手取り額」に着目する必要があります。
不動産クラウドファンディングでは、原則として源泉徴収(20.42%)が行われますが、確定申告をすることで控除を受けられる場合があります。
まとめ|3~8%の安定利回りを“分散×長期”で着実に積み上げよう
今回紹介した不動産クラウドファンディングにおける利回りについて、重要なポイントを5つにまとめました。
- 不動産クラウドファンディングの平均利回りは3~8%で、他の金融商品より高水準
- 利回りには「想定利回り」と「実質利回り」の違いがあるため注意が必要
- 物件種別・立地、運用期間、劣後出資割合などが利回りに影響
- 利回り最大化のコツは、複数サービス活用、キャンペーン活用、税務対策
不動産クラウドファンディングに興味を持たれた方は、サービスごとの特徴やリスクを比較して、小額で投資することから始めてみましょう。
上場企業運営の不動産クラウドファンディング「CREAL(クリアル)」が、Amazonギフトカードのプレゼントキャンペーンを実施中です!

投資家登録だけでも2,000円分のアマギフ、初回投資額に応じて最大48,000円分のアマギフがもらえます。
合計で最大5万円分のギフト券をもらえるお得な内容です。
不動産クラファンを始めたい!という方は、この機会にCREALへの登録を検討してみてはいかがでしょうか。