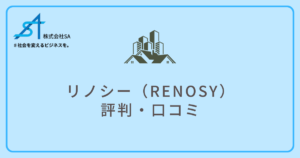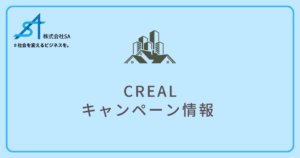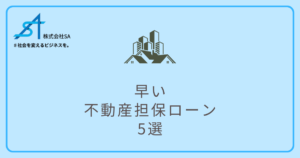「不動産クラウドファンディングとソーシャルレンディングの違いがよくわからない」
「どちらに投資すべきか、判断基準が知りたい」
このような悩みを抱えていませんか?
本記事では、不動産クラウドファンディングとソーシャルレンディングの仕組みや違いを徹底的に解説し、あなたに最適な投資先を見つけるお手伝いをします。
上場企業運営の不動産クラウドファンディング「CREAL(クリアル)」が、Amazonギフトカードのプレゼントキャンペーンを実施中です!

投資家登録だけでも2,000円分のアマギフ、初回投資額に応じて最大48,000円分のアマギフがもらえます。
合計で最大5万円分のギフト券をもらえるお得な内容です。
不動産クラファンを始めたい!という方は、この機会にCREALへの登録を検討してみてはいかがでしょうか。
不動産クラウドファンディングとソーシャルレンディングの仕組み
不動産クラウドファンディングとソーシャルレンディングの大まかな仕組みは以下の通りです。
- 投資家から資金を集める
- その資金で不動産を取得・運用する
- 運用で得た賃料や売却益を投資家に分配する
- 投資家は不動産の所有権を持たず
- 投資家から資金を集める
- その資金を企業や個人に貸し付ける
- 借り手は利息を支払う
- 投資家はその利息収入を配当として受け取る
- 貸付先の返済能力によってリスクが左右される
不動産クラウドファンディングの基本(匿名組合・任意組合スキーム)
不動産クラウドファンディングには、主に「匿名組合型」と「任意組合型」の2つのスキームがあります。
匿名組合型
投資家は事業者と匿名組合契約を結んで出資し、事業者が不動産の運用を行う組合です。
なお、投資家は利益の分配を受けますが、不動産の所有権を持たず、運用にも関与しません。
また、損失が出た場合でも、出資額以上の責任を負うことはありません。
任意組合型
投資家と事業者が任意組合契約を結び、共同で不動産の運用を行います。
投資家は不動産の持分を所有し、運用にも関与できるのです。
ただし、損失が出た場合、出資額以上の責任を負う可能性があります。
不動産を所有したことになるため、税効果を受けられることもあります。
選び方は好みですが、任意組合型は確定申告が必須になりますので、投資初心者の方は、「匿名組合型」から始めることをおすすめします。
ソーシャルレンディングの基本(貸付型クラウドファンディング)
ソーシャルレンディングは、投資家から集めた資金を、資金を必要とする企業や個人に貸し付ける仕組みです。
貸付先は、事業資金や不動産取得資金など、さまざまな目的で資金を活用します。
一方、投資家は貸付先からの利息収入を得ることができます。
ただし、貸付先の返済能力に依存するため、貸し倒れのリスクがあるので、注意が必要です。
5つの違いで徹底比較
不動産クラウドファンディングとソーシャルレンディングの主な違いを、以下の5つの観点から比較します。
- 投資対象とリスク構造の違い
- 配当原資と収益モデルの違い
- 元本保護スキーム(優先劣後・担保保証)の違い
- 情報開示・ガバナンス体制の違い
- 根拠法・監督官庁など規制面の違い
投資対象とリスク構造の違い
投資対象や、どういったことがリスクになるのかにも違いがあります。
不動産クラウドファンディング
投資対象は不動産であり、物件の運用によって収益を得ます。
対象不動産が空室になったり、売却価格が下がったりすると、利回りの低下や元本割れにつながります。
ソーシャルレンディング
投資対象は企業や個人への貸付であり、利息収入が主な収益源です。
そのため、貸付先の返済能力により、収益が左右されます。
なお、企業に返済能力がなくなるなどした場合、貸し倒れのリスクがあります。
配当原資と収益モデルの違い
投資対象が違うため、配当になるものや、収益モデルも異なります。
不動産クラウドファンディング
不動産の運用による収益(賃料収入や売却益)が配当原資です。
そのため、物件の運用状況や市場環境により、収益が変動します。
ソーシャルレンディング
貸付先からの利息収入が配当原資です。
ただし、貸付先の返済能力に依存するため、収益が不安定になる可能性があります。
元本保護スキーム(優先劣後・担保保証)の違い
どちらも元本保証がないことは共通していますが、保護スキームは異なります。
不動産クラウドファンディング
優先劣後方式を採用している場合、損失が出ても事業者が優先的に損失を負担するため、投資家の元本が一定保護されるのが特徴です。
劣後出資割合が高いほど、リスクが軽減されていると言えます。
ただし、全ての案件において優先劣後が適用されているわけではないので、注意しましょう。
ソーシャルレンディング
担保や保証を設定している場合があります。
そのため、貸し倒れリスクを軽減するために、担保や保証の有無を確認することが重要です。
情報開示・ガバナンス体制の違い
情報開示にも異なる点があります。
不動産クラウドファンディング
投資対象の不動産情報や運用状況が比較的詳細に開示されます。
そのため、投資家は物件の情報を確認して投資することが可能です。
ソーシャルレンディング
貸付先の情報が限定的にしか開示されない場合があります。
これは、貸金業法上の制約により、貸付先の詳細情報を開示すると、投資家が貸金業者とみなされる可能性があるためです。
根拠法・監督官庁など規制面の違い
不動産クラウドファンディングも、ソーシャルレンディングも少額で投資でき、運用期間中はほったらかでいいなど、似たような投資スタイルですが、法律は全く異なります。
不動産クラウドファンディング
不動産クラウドファンディングは、不動産特定共同事業法(不特法)に基づく制度です。
そのため、国土交通省の監督を受けます。
そのため、事業者は不特法に基づく許可を取得し、適切な運営を行う必要があります。
ソーシャルレンディング
一方、ソーシャルレンディングは、金融商品取引法および貸金業法に基づく制度です。
そのため、事業者は、第二種金融商品取引業および貸金業の登録を行い、適切な運営を行わなければなりません。
利回り・手数料・流動性を表で比べる
不動産クラウドファンディングとソーシャルレンディングの違いを、
- 想定利回りと変動幅(実績レンジ)
- 手数料・税制・源泉徴収の扱い
- 募集頻度・途中解約可否と資金拘束期間
という3つの観点で比較します。
想定利回りと変動幅
| 不動産クラウドファンディング | ソーシャルレンディング | |
|---|---|---|
| 利回り | 3~8% | 5~10% |
| 利回りの変動 | 運用期間中の変動なし ※対象不動産の運用状況や市場変化により変更する可能性あり | 運用期間中の変動なし ※貸付先の状況により変更する可能性あり |
利回りは大きな差はありませんが、どちらかというとソーシャルレンディングの方が高い傾向にあります。
不動産クラウドファンディングに比べ、ソーシャルレンディングは海外案件も多いため、ハイリスク・ハイリターン案件も多くなります。
また、どちらも運用期間中に利回りは変動することなく、ほったらかしで投資することが可能です。
しかし、不動産価格の下落や貸付先企業の状況などにより、利回りが下がることは十分考えられます。
手数料・税制・源泉徴収の扱い
| 不動産クラウドファンディング | ソーシャルレンディング | |
|---|---|---|
| 手数料 | 入金・出金手数料のみの場合がほとんど | 入金・出金手数料のみの場合がほとんど |
| 税金・源泉徴収 | 雑所得 分配金は源泉徴収された状態で入金される | 雑所得 分配金は源泉徴収された状態で入金される |
こちらはどちらも同じでした。
確定申告の際は、すべての雑所得を合計して計算する必要があります。
募集頻度・途中解約可否と資金拘束期間
| 不動産クラウドファンディング | ソーシャルレンディング | |
|---|---|---|
| 募集頻度 | 1ヶ月に1件程度(サービスにより異なる) | 1ヶ月に5件程度(サービスにより異なる) |
| 中途解約 | 原則不可 ※一部可能なサービスもあり | 原則不可 |
募集頻度はサービスによって異なりますが、一般的にはソーシャルレンディングの方が募集頻度は高いでしょう。
不動産クラウドファンディングの場合、不動産の仕入れが必要なため、同時に複数案件を進めることがソーシャルレンディングよりも難しいです。
また、不動産クラウドファンディングは共同出資制度である優先劣後方式を取り入れているため、1案件につきお金がかかります。
中途解約についてはどちらもほとんどの事業者において原則不可です。
不動産クラウドファンディングには一部中途解約の可能なサービスもあります。
メリット・デメリット整理
不動産クラウドファンディングとソーシャルレンディング、それぞれの特徴を踏まえて、メリットとデメリットを整理しておきましょう。
不動産クラウドファンディングのメリット/デメリット
不動産クラウドファンディングのメリット・デメリットは以下のとおりです。
- 不動産の裏付けがあるため、安定的な収益が見込める
- 優先劣後スキームによって元本保護がある程度期待できる
- 匿名組合型により、運用の手間がかからない
- 利回りが控えめで、ハイリターンを求める人には不向き
- 途中解約が原則不可で、資金拘束がある
- 物件や事業者の選定によって成果が左右される
ソーシャルレンディングのメリット/デメリット
ソーシャルレンディングのメリット・デメリットは以下のとおりです。
- 高利回り案件が多く、短期間での運用も可能
- 投資対象が多様で、ポートフォリオ分散がしやすい
- サービスによっては少額から投資可能
- 貸し倒れリスクが高く、元本保証がない
- 貸付先の情報が限定的で、投資判断が難しいこともある
- 途中解約不可のため、流動性に乏しい
どちらが向いている?投資家タイプ別チェックリスト
投資家の目的や性格によって、どちらが適しているかは異なります。
そこで、以下の3つの観点から、自分に合った投資スタイルを探ってみましょう。
- 安定志向で物件裏付けを重視する人に向く選択肢
- 高利回り・短期運用を狙う人に向く選択肢
- 分散投資で双方を組み合わせる戦略
安定志向で物件裏付けを重視する人に向く選択肢
- 元本の安全性を重視したい
- 長期でコツコツ資産形成したい
- 物件や不動産市場に関心がある
このような投資家には、不動産クラウドファンディングが向いています。
高利回り・短期運用を狙う人に向く選択肢
- リスクを取ってもリターンを最大化したい
- 数ヶ月~1年以内の短期運用をしたい
- 投資回転率を高めたい
このような投資家には、ソーシャルレンディングがおすすめです。
分散投資で双方を組み合わせる戦略
- 安定収益と高利回りの両方を狙いたい
- 投資リスクを抑えつつ収益性を確保したい
- 市場環境に応じて運用先を柔軟に変えたい
また、双方をバランスよく組み合わせることで、安定性と成長性を同時に追求する戦略が可能です。
はじめ方&サービス選定ガイド
不動産クラウドファンディングもソーシャルレンディングも、基本的な始め方は共通していることが多いです。
ここでは、基本的な始め方について紹介します。
共通フロー(口座開設~入金~投資)
不動産クラウドファンディングとソーシャルレンディングの始め方の共通フローは、以下の通りです。
- サービスの会員登録を行う(本人確認書類の提出が必要)
- 投資用口座の開設と本人確認を完了させる
- 自分の銀行口座から入金
- 案件を選定し、出資申込を行う
- 投資が実行され、運用開始
- 分配金の受け取り(運用終了後、元本返還)
比較表のチェックポイント5項目
プラットフォームを選ぶ際は、以下の5点を比較するのが効果的です。
- 想定利回りとリスク水準
- 優先劣後スキーム・担保保証の有無
- 情報開示の詳細さ・信頼性
- 運用期間と資金拘束の柔軟性
- 過去の実績や運営会社の信頼性
まとめ|違いを理解し、自分に合うプラットフォームを選ぼう
今回紹介した「不動産クラウドファンディングとソーシャルレンディングの違い」について、重要なポイントを5つにまとめました。
- 不動産クラウドファンディングは不動産を裏付けとした投資で、安定性が高い
- ソーシャルレンディングは貸付型で、高利回りの反面リスクも高い
- 投資目的やリスク許容度に応じて適切な商品を選ぶことが重要
- 両者には配当原資や規制の違いがあり、仕組みを理解する必要がある
- プラットフォームの信頼性や実績も選定の重要な指標になる
それぞれの特性を理解した上で、「自分に合った投資スタイル」を選びましょう。
上場企業運営の不動産クラウドファンディング「CREAL(クリアル)」が、Amazonギフトカードのプレゼントキャンペーンを実施中です!

投資家登録だけでも2,000円分のアマギフ、初回投資額に応じて最大48,000円分のアマギフがもらえます。
合計で最大5万円分のギフト券をもらえるお得な内容です。
不動産クラファンを始めたい!という方は、この機会にCREALへの登録を検討してみてはいかがでしょうか。